
共創型・士業勉強会「Knowledge Cross(通称:ナレクロ)」のLINEスタンプが発売されました👏
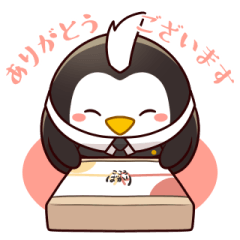
LINEスタンプ
LINE STORE でスタンプをチェック
実はこのLINEスタンプの制作にデザイン担当として関わらせていただいております。
そのご縁で、ナレクロのNoteに著作権の記事も掲載していただきました!
知財に詳しい他士業の先生から助言をいただくことも出来て、私自身が著作権について改めて理解を深める機会にもなりましたので、今回こちらのブログで共有できたらと思います。
ということで、今回は
LINEスタンプを作りたいけれど、「著作権ってどうなるの?」「誰かと共同制作する場合の権利は?」
といった疑問をお持ちの方向けの記事となります!
クリエイターや作家の方が安心してLINEスタンプ制作に取り組めるよう、著作権と商標の基本から実務的な対策まで、分かりやすく解説します。
目次
1. 著作権と著作者人格権の違い
まず、多くのクリエイターが混同しがちな「著作権」と「著作者人格権」の違いを整理しましょう。
基本的な権利の構造
| 権利名 | 内容 | 譲渡 |
|---|---|---|
| 著作権 | 利用許可、販売、複製等 | できる(契約でOK) |
| 著作者人格権 | 名前の表示、改変拒否等 | できない(法律で禁止) |
よくある誤解を解消
「著作権を譲渡したら、もう何も言えない」と思われがちですが、これは間違いです。
著作者人格権は創作した本人だけが持てる権利で、譲渡することはできません。
ただし、契約により「著作者人格権を行使しない」という合意は可能です。この区別を理解することが、適切な契約書作成の第一歩となります。
2. 共同制作時の権利関係
では例えば、役割分担による共同制作の場合の著作権はどうなるのでしょうか?例えば下記のような事例です。
- Aさん:ラフ案・アイデア担当(受託者)
- Bさん:清書・仕上げ担当(受託者)
- C社:イラストの利用者、支払者(委託者)
このような場合、作品はAさんとBさんの共同著作物となり、C社がその対価を支払う形になります。
C社が著作物を扱う際、原則として両者の許諾が必要になります。
権利関係をクリアにする方法
共同制作をスムーズに進めるには、以下の契約条項が重要です。
✅ 著作権の明確な譲渡
「本件成果物に関する著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)は、すべて委託者に譲渡する」✅ 著作者人格権の不行使合意
「受託者は著作者人格権を行使しないことに同意する。ただし、ポートフォリオへの掲載は認めるものとする」あくまで人格権は創作者個人に属するため、譲渡は不可であることを忘れずに。ただ、氏名表示権の行使までは認めないのが一般的です。
例えばソシャゲのイラストにはイラストレーターの氏名(クレジット)が載っていないことが多いですよね。
一方で、ご本人のSNSで「描きました!」と紹介されているのは、「委託者が公表した後、受託者自身の作品としてポートフォリオとして掲載して良い」と契約を交わしているためかと思います。
ここで更に別の例を考えてみましょう。
用途外の利用と、人格権侵害の関係についてです。
たとえば「雑誌C」の表紙のイラストを頼まれて描いたはずなのに、「雑誌D」の表紙のイラストとして使われてしまった場合の人格権は侵害されるのでしょうか?
✅ 用途外利用で著作者人格者の権利は侵害されるか
実は、どれだけ「雑誌C」の表紙のイラストに使って欲しかったとしても、名誉や信用を害さない限りは人格権侵害に該当しません。
ただし、「雑誌Cのみに使用する」と契約書を交わしていれば、それは契約違反となります。
人格権侵害と契約違反は別概念として区別し、契約書では使用目的を明確に限定することが必要です。
3. LINEスタンプ特有の商標問題
今回LINEスタンプの作成・販売に関わらせていただくにあたり、「商標」については盲点でした。
実は、LINEスタンプの中にあるセリフや文字にも注意が必要です。意外な言葉が商標登録されており、使用すると審査で落ちる可能性があるんです。
要注意!登録商標の例
例として、LINEスタンプで実際にNGとなる表現に「スクショ」があります。
実は「スクショ」はGMOの登録商標。商標となっている言葉をセリフに使っていると、販売NGとなってしまいます。
ちなみに「LINEしてね」の「LINE」も商標。罠すぎますね。
セリフ表現は「言語表現」であっても、商標法的には実務上の対策として完全な避けられません。実際にはLINE測定のガイドラインや利用継続した検証が重要になります。
気になる商標チェックの方法は?
制作前に以下の手順で確認しましょう!
- J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)で検索
- 使用予定の文字・フレーズを調査
- 登録商標に該当する場合は代替表現を検討
ここまでに記載した内容を、ナレクロではより詳しくNoteにまとめてくださっています。興味のある方はぜひ覗いてみてくださいね。
4. まとめ。契約書で押さえるべき5つのポイント
適切な契約書は、クリエイターの権利を守る重要なツールです。今回はイラストをメインで取り上げて説明しましたが、何かを創作する時に、創作者となる方には気を付けていただきたいポイントをまとめてみました。
必須項目チェックリスト
✅ 1. 著作権の範囲
- 利用許諾か完全譲渡かを明確化しましょう
- 二次利用権(第27条・28条)も含むか確認しましょう
✅ 2. 著作者人格権の取り扱い
- 著作者人格権の不行使の合意内容は適切か確認しましょう
- ポートフォリオ掲載等の例外規定が必要であれば依頼者に伝え、契約書を巻きなおしましょう
✅ 3. 使用範囲の限定
- 著作物の利用目的を限定する必要があるか確認しましょう
- 商用利用は別途協議する旨が必要か確認しましょう
- 期間の制限が必要か確認しましょう
✅ 4. 権利非侵害保証
- 契約をする相手と自分、お互いが第三者の権利を侵害していない旨の保証を記載しましょう
- 問題発生時の責任分担を明示しましょう
✅ 5. 対価と支払い条件
- 買い切りか継続的な対価かを取り決めましょう
- 支払いタイミングと方法について明確に記載しましょう
契約書ひな形の活用
とはいえ、契約書なんて普段気にせず創作を楽しんでいる方も多いかと思います。
いざ必要になった時は、文化庁の「著作権契約書ひな型作成支援システム」を活用すると、適切な契約書を効率的に作成できます。自分用のひな形を持っておくことで、相手方から提示された契約書との比較検討も可能になります。
5. トラブル回避のための実践的チェックリスト
ここからはさらに詳しく、実際にお手元に契約書がある方向けの内容です。
個別具体的な内容を網羅しているわけではないので、何か不明な点があれば、著作権に詳しい行政書士や弁護士にご相談されることをお勧めします。
著作物を制作する前のチェック項目
- 共同制作者がいる場合、役割分担が明確か
- 著作権の帰属について合意があるか
- 使用予定の文字・セリフに商標問題はないか
- 契約書の内容を双方が理解しているか
- 納期と対価について認識が一致しているか
制作中のチェック項目
- 参考資料の著作権をクリアしているか
- キャラクターデザインに既存作品との類似性はないか
- セリフに不適切な表現は含まれていないか
完成後のチェック項目
- 最終的な権利関係が契約書通りか
- LINEの審査ガイドラインに準拠しているか
- 今後の展開について合意があるか
まとめ:安心できる創作環境を作るために
LINEスタンプ制作における著作権や商標の問題は、事前の準備と適切な契約により回避できます。
重要なポイントの再確認
- 著作権は譲渡可能、著作者人格権は譲渡不可
- 共同制作では契約で権利関係を明確化
- 商標登録された言葉の使用に注意
- 自分用の契約ひな形を用意
- トラブル発生時は専門家に相談
創作活動は本来楽しいものです。適切な知識と準備により、権利関係の不安なく制作に集中できる環境を整えましょう!
